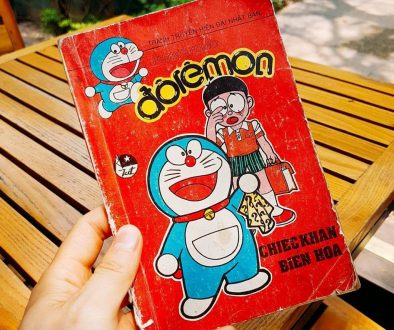2014年2月:フィールドノーツ(3)久松ことばと時代の変化 Fieldnotes 3 Miyako Island
今日は久松・宮古島での最終日。
荷物をまとめ、民宿で自転車を借りて、浜に向かう。昨日のおじいに会えるだろうか。
この浜はパイカジの話をしてくれたおじいがいた、漁船がたくさんあるいわば久松の中心的漁港からは少し離れている。浜には、漁から戻ったらしい小ぶりのボート(レジャーボートと言っていた)の横で、おじいとは呼べない40,50代の男性二人が網を広げて、網についた海藻や珊瑚を手でとり、漁の後始末をしていた。
そのすぐそばで、昨日のおじいが、波打ち際に座って、魚の内臓を包丁で掻きだしていた。「今日は漁にいったんですか」と声をかけると手を休めずに、いいや、そこの人たちからもらったとのこと。おじいはもくもくと魚4匹の内臓を出しながら、海水で魚を洗っている。「どうやって食べるの?」、「煮つけがいいな」。
作業が終わるとおじいはすくっと立って、魚をくれたボートの男性二人に話しかける。このときに私は初めて生きた久松ことばをこの耳で聞いた。「久松ことばについて」、宮古島の人たちからは聞いていたが、久松ことばが実際の生活の中で使われている場面に出くわして、一瞬、稲妻に打たれたような衝撃を感じる。やさしい話し方。やわらかい音の塊。その応答が会話として進んでいる。日本国内でもめずらしい「ん」から始まることばもあると言われている。でも私の考えていた「ん」ではなかった。頭の中で新しい音の響きがめぐった。
おじいは「この人に聞くのがいいよ」と私を紹介してくれると、さっさと魚をもって、軽トラックに乗ってしまった。ぼんやりしていた私は慌てて、手を振った。手を振り返してくれたのを確認して、ほっとする。本当はまだまだ、おじいの久松ことばを聞きたかったなあ・・・。
(おじいと呼ぶのには若い方なので)Nさんは、私に「この魚あげようか」とその日に漁に出て釣った大きい魚をくださろうとする。これから飛行機で東京に帰るので、生魚は持って帰れない。「お気持ちだけ」というと、「冷凍すれば持って帰れるよ、分かっていたら冷凍しておいてあげたのに」。何度も持って帰ったらと勧めてくれる。
Nさんに、私が久松の子どもたちに会いにきたこと、久松の集落を歩きまわって、前日におじいに会ったこと。今朝は、おじいに会えるかとまた戻ってきたというと、「もう友達だから、次にきたときは刺身にして食べさせてあげるから家に来なさい」といってくれる。
もともとは多良間島出身のNさんは、地元の人が前よりも魚はないからと一向に漁に出ない様子をみて、「いや魚はあるはずだから漁にでる」と小さいレジャーボートで漁をするようになったという。その後、地元の久松の若い人たちが自分たちで漁をする仲間を募って、このごろはグループで漁にでるようになったさと嬉しそうだった。実際に漁にでてみなくてはわからないさというNさんの行動が久松の若者たちを動かしたのだろう。
別れ際に、なぜおじいに魚を分けてあげたのかをNさんに尋ねると、「魚を一人占めするといけないさ、竜宮の神様が見ているからね、もう魚が獲れなくなってしまう。他の人にも分けてあげるのがいいさ」「時々自分が知り合った本土からの人にも魚をあげるよ」。竜宮の神様は漁と共に生きている。「竜宮の神様は生きているんですね」「そうさ、見ているよ」。
久松ことばは、一つの集落で使われていることばではあるが、その集落が培った文化、風土、歴史に当然ながら結びついている。久松で栄えた漁業の終焉と共に、また、新たに久松にやってきた別の地域の人たちの増加に伴って、地域全体での生活言語ではなくなってきた。久松ことばに関わる文化や歴史はまだ漁に関わる人たち、70,80歳代の人たちの間では話されている。これからは、現在、久松ことばを話せる人たち、その「家族」の一人一人が自分の使いたい久松ことばを残す、または、おじい、おばあのことばとして記憶に留めることになるのだろう。それでも、地元の学校、老人会や公民館などが伝えていこうという「意志」を持つ限り、久松ことばはお祭り、クイチャーなどの地域文化に関わる語彙として必ず地元の人の中に残ることは確かだ。「話しことば」として残るかどうか、どのていど残すことができるのか、または消えていくのか。久松ことばの変化(ダイナミズム)と温かい集落の人たちに、私はこれからも会いにこよう。